介護給付
(カイゴキュウフ)
要介護(要介護1~5)の認定を受けた利用者(被保険者)が利用できるサービスとその利用料を保険料・税金から補助(支給)すること(保険給付)をいう。原則、利用料の9割または8割が補助され、残りの1割または2割が利用者の自己負担となる。
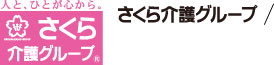


(カイゴキュウフ)
要介護(要介護1~5)の認定を受けた利用者(被保険者)が利用できるサービスとその利用料を保険料・税金から補助(支給)すること(保険給付)をいう。原則、利用料の9割または8割が補助され、残りの1割または2割が利用者の自己負担となる。
(カイゴサービスジョウホウノコウヒョウセイド)
利用者が適切にさまざまなサービスを選択することができるよう、介護保険制度下のサービスを提供するすべての事業所・施設にサービス内容や運営状況等に関する情報の公表を義務づける制度。介護サービス情報は、職員体制、利用料金、サービス提供時間など事業者が自ら記入する「基本情報」と、調査員が事業所・施設を訪問してサービスに関するマニュアルの有無、提供内容・時間の記録など事実かどうかを客観的に調査する「運営情報」とで構成され、都道府県が指定する情報公表センターからインターネット上に公表される。
(カイゴシエンセンモンイン)
介護保険制度で、利用者の生活や介護に関する相談に応じるとともに、利用者がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市区町村、サービスを提供する事業所、施設などとの連絡調整等を行う人のこと。「介護支援専門員」は、ケアマネジャーの仕事に必要な資格の名称でもある。
(カイゴフクシシ)
社会福祉士及び介護福祉士法によって創設された、サービスを提供する事業所・施設の介護職員などが取得する、介護専門職の国家資格。介護福祉士の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識および技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に心身の状況に応じた介護(2015(平成27)年度からは喀痰吸引等を含む)を行い、並びにその者およびその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。資格取得のためには、介護福祉士養成施設を卒業するか介護福祉士国家試験等の合格が必要となる(2015(平成27)年度からは養成施設卒業者も国家試験合格が必要)。
(カイゴホケンセイド)
加齢に伴い要介護状態または要支援状態に陥ることを保険事故(この制度の保険料・税金で補助する生活上の出来事)とする保険制度の総称。社会保険の一つ(他には、年金保険、医療保険、雇用保険、労災保険がある)。介護保険は、被保険者の要介護状態や要支援状態に関して必要な保険給付(サービスの利用料を保険料・税金で補助すること)を行う。
(カイゴホケンリョウ)
介護保険事業に要する費用に充てるために拠出する金額で、市区町村(保険者)が被保険者から徴収する。第1号被保険者の保険料は、一定の基準により算定した額(基準額)に所得に応じた率を乗じて得た額となる。第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づき算定した額となり、医療保険の保険料と一括して徴収される。
(カイゴヨボウサービス)
介護予防サーピスとは、要介護状態になることをできるだけ防ぐとともに、要支援状慇になっても状鰈の懇化を防ぐことに重点をおいたサービス。要介護認定・要支援認定で「要支援1」 「要支援 2 」に認定された人が利用するサービスに相当する。
(カイゴヨボウ・ニチジョウセイカツシエンソウゴウジギョウ)
市区町村が介護予防および日常生活支援のための施策を総合的に行えるよう、2011(平成23)年の介護保険制度の改正において創設された事業で、2014(平成26)年の制度改正により新たに再編成され、現在は、「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」からなっている。介護予防・生活支援サービス事業には、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス(配食サービス等)、介護予防ケアマネジメント(ケアマネジャーによるケアプラン。地域包括支援センターで行う)があり、要介護(要支援)認定で「非該当」に相当する第1号被保険者(高齢者)や要支援1・2と認定された被保険者を対象とする。介護予防訪問介護と介護予防通所介護がそれぞれ訪問型サービス、通所型サービスに移行するとともに、この新しい介護予防・日常生活支援総合事業は、2017(平成29)年3月末までに全市区町村で実施するよう、各市区町村で整備が進められている。
(ケアプラン)
要介護(要介護1~5)の認定を受けた利用者(被保険者)が利用できるサービスとその利用料を保険料・税金から補助(支給)すること(保険給付)をいう。原則、利用料の9割または8割が補助され、残りの1割または2割が利用者の自己負担となる。
(ケアマネジメント)
生活困難な状歴になり頃助を必要とする利用者か、 迅速かつ効果的に 、 必要とされるすべての保健・医療・福祉サービス等を受けられるように調整することを目的とした援助展間の方法。①インテーク(導入)、②アセスメント(課題分析)の実施、③ケアプラン原案の作成、④サービス担当者会議の開催、④ケアプランの確定と実施(ケアプランに沿ったサービス提供)、⑤モニタリング(ケアプランの実施状況の把握)、⑥評価(ケアプランの見直し)、⑦終了、からなる。利用者と社会資源の結び付けや、関係者・関係機関・施設との連携において、この手法が取り入れられている。介護保険制度下においては、居宅介護支援や介護予防支援(地域包括支援センター)、介護保険施設などで行われている。
(ケアマネジャー)
介護保険制度で、利用者の生活や介護に関する相談に応じるとともに、ケアマネジメントという手法を用い、利用者がその心身の状況に応じた適切なサービスを利用できるよう市区町村、サービスを提供する事業所、施設等との連絡調整を行う人のこと。
(コクミンケンコウホケンダンタイレンゴウカイ)
国民健康保険の保険者が共同してその目的を達成するために設立している公法人です。各都道府県ごとに設置されている.介護保険上の業務としては、①介護サービス費の請求に対する審査・支払い。②介護サービスの質の向上に関する調査とサービス事業者・施設に対する指導・助言(オンブズマン的業務)がある。そのほかに、第三者行為に対する損害賠償金の徴収・収納事務、指定居宅サービス・指定居宅介護支援事業や介護保険施設の運営、介護保険事業の円滑な運営に資する事業を行うことができます。


(サービスタントウシャカイギ)
ケアプランの作成にあたってケアマネジャーが開催する会議。利用者とその家族、ケアマネジャー、ケアプランに位置づけた、利用者のサービス提供に関連する事業所の担当者等から構成される。ケアマネジャーによって課題分析された結果をもとに、利用者と家族に提示されるケアプランの原案を協議し、利用者の同意を得てケアプランを確定し、ケアプランに沿ったサービス提供につなげる。また、その後、利用者や家族、サービスの担当者がケアプランの見直しが必要と考えた場合には、担当者会議が要請され適宜開かれる。
(サービステイキョウセキニンシャ)
訪問介護(ホームヘルプサービス)事業所の柱となる職種。介護福祉士などの資格を有する。利用者宅に出向き、サービス利用についての契約のほか、利用者を担当するケアマネジャーと連携しながら、アセスメントを行い、ケアプランに沿って作成する、具体的なサービス内容や手順、留意点などを記した訪問介護計画(個別援助計画)の内容についての話し合いなどを行う。また、実際のサービス提供に関して訪問介護員(ホームヘルパー)への指導・助言、能力開発等の業務も行う。
(ザイタクカイゴ)
病気・陣害や老化のために生活を自立して行うことができない人が、自分の生活の場である住み慣れた自宅(家庭)において、介護を受けること。または、その人に対して、自宅(家庭)で介護を提供すること。利用者の持つ多面的なニーズに対応しやすく、ノーマライゼーションの観点からも重要な介護の場である。
(ザイタクカイゴシエンセンター)
老人福祉法に基づく老人福祉施設の一貫で 、 在宅介護支援センターとして規定されているが.地域の老人の福祉に関する問題について. 在宅の要援護高齢者や要援護となるおそれのある高齢者またはその家族等からの相談に応し、それらの介護等に関するニーズに対応した保健・福祉サービス(介謹保険を含む)が、 総合的に受けられるように市区町村等関係行政機関・サービス提供機関・居宅介護支援事業所等との連絡調整等を行う。これらの役割は現在、 2006年に創設された地域包括支援センターが担っており 、 在宅介護支援センターの統廃合が進んでいる。
(シャカイフクシキョウギカイ)
社会福祉法の規定に基づき組織される、地域福祉の推進を目的とする団体で一般的には、「社協」の略称で呼ばれる場合が多い。市区町村を単位とする市区町村社会福祉協議会、指定都市の区を単位とする地区社会福祉協議会、都道府県を単位とする都道府県社会福祉協議会がある。社会福祉を目的とする事業を経営する者および社会福祉に関する活動を行う者が参加するものとされており、さまざまな福祉サービスや相談、ボランティア活動や市民活動の支援、共同募金など、地域の福祉の向上に取り組んでいる。介護保険制度下のサービスを提供している所も多い。
(シャカイフクシシ)
社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者。社会福祉の専門的知識および技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者、または医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡および調整その他の援助を行う専門職である。介護保険制度においては、市区町村の地域支援事業における包括的支援事業を適切に実施するため、地域包括支援センターに配置されている。
(ショウカンバライ)
福祉や医療のサービスにおいて、利用者が、サービスに要する費用(利用料)の全額を、いったんサービス提供事業者に支払い、その後、申請により、保険者から自己負担分を除いた額について、払い戻しを受けること。介護保険制度においては、現物給付が原則である一方、特定(介護予防)福祉用具販売と(介護予防)住宅改修の利用時や、1割または2割・3割の自己負担の合計が高額になった場合の高額介護(介護予防)サービス費、要介護認定の効力が生じる前にサービスを利用した場合の特例サービス費を受けるときなどに、この方式をとる。
(シンタイコウソク)
介護サービス等の利用者の行動を制限する行為である。例えば、車いすやベッドに縛って固定すること、特別な衣服によって動作を制限すること、過剰に薬剤を投与し行動を抑制すること、鍵付きの部屋に閉じこめることなどが該当する。身体拘束は、利用者に対して身体的・精神的・社会的な弊害をもたらすことが多いことから、介護保険制度では、身体拘束を原則禁止している。
(ジュウショチトクレイ)
介護保険制度や国民健康保険において、介護保険施設や特定施設(〔介護予防〕特定施設入居者生活介護等)、病院などに入所(入院)することにより、当該施設所在地に、住所を変更(住民票を移動)したと認められる被保険者については、(本来であれば、住民票のある市区町村〔保険者〕の被保険者となるが、)住所変更以前の住所地である市区町村(保険者)の被保険者とする特例措置。介護保険制度では、施設が所在する市区町村に高齢者が集中し、その市区町村の保険給付費ひいては保険料負担が増加することで、市区町村間の財政上の不均衡が生じることを防ぐために設けられた。2か所以上の住所地特例施設に入所した場合は、最初の施設に入所する前の住所地であった市区町村が保険者となる。
(セイカツソウダンイン)
介護保険制度下では、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や通所介護事業所、短期入所生活介護事業所などに配置され、利用者の相談援助等を行う者をいう。社会福祉主事任用資格を有する者または同等以上の能力があり、適切な相談援助等を行う能力を有すると認められる者とされている。
(ゼンコクシャカイフクシキョウギカイ)
社会福祉協議会の全国組織。社会福祉法における「社会福祉協議会連合会」にあたる。国の機関(厚生労働省等)との協議、都道府県や市区町村の各社会福祉協議会との連絡・調整、福祉に関する調査・研究、出版などの活動を行っている。一般的には、「全社協」の略称で呼ばれる場合が多い。
(ソーシャルワーカー)
一般的には社会福祉従事者の比称として使われることが多いが濯祉僑埋に坦づき、専門的な知識・技術を有して社会福祉補助(相談援助者等)を特定専門者を指すこともある。資格としては、社会福祉主事任用目格や社会場祉士などを有している者が 多い。


(ダイイチゴウホケンリョウ)
介護保険制度において、市区町村が第1号被保険者(65歳以上の者)から徴収する介護保険料。その被保険者が属する保険者(市区町村)の保険給付の財源に直接充当される。保険料の額は、各市区町村が定める。保険料の徴収方法は、 年金額が 18万円以上(年額)の人は年金からの天引き(特別徴収)、それ以外は市区町村による普通徴収で行われる。
(ダイ二ゴウホケンリョウ)
介護保険制度において、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の者の医療保険加入者)から徴収する介護保険料。医療保険者により、医療保険料と一体的に徴収される。
(ダイリジュリョウ)
本来、被保険者に対して支払われる保険給付費用を、サービスを提供した事業所・施設が、代わりに受け取ること。介護保険制度は、代理受領による現物給付を原則としている。
(チイキシエンジギョウ)
介護保険制度において、被保険者が要介護状態や要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、市区町村が行う事業。「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」からなる。
(チイキホウカツシエンセンター)
地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を行うことを目的として設けられた施設。市区町村および老人介護支援センターの設置者、 一部事務組合、医療法人、社会福祉法人などのうち、包括的支頃事業の委託を受けたものが設置することができる。主な業務は、 ①包括的支援事業(介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務). ②介護予防支援、③要介護状態等になるおそれのある高齢者の把握などで、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職が配置されている 。


(ニチジョウセイカッドウサ)
ADL(エーディーエル)
Activities of Daily Livingの略称で、日常生活動作ともいう。人間が毎日の生活を送るための基本的動作群のことであり、具体的には、①身の周り動作(食事、更衣、整容、トイレ〔排せつ〕、入浴の各動作)、②移動動作、③その他(睡眠、コミュニケーション等)がある。ADLとは別に、家事動作や管理能力、交通機関の利用など、生活の中の応用的な動作群を、IADL(手段的日常生活動作)という。なお、Aは動作(アクティビティ)、DLは日常生活(デイリーリビング)、Iは手段(インストラメンタル〔Instrumental〕)の意味である。


(フクシヨウグセンモンソウダンイン)
介謹保険法に塁づく福祉用具貸与事業および特定福祉用具販売事業において、 福祉用具の専門的知識を有し、 利用者に適した用具の選定に関する相談を担当する者。事業所ごとに2人以上福祉用具専門相談員を配置が必要とされている。専門相談員は福祉用具専門相談員、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、ホームヘルパー(2級以上)等。または指定講習(福祉用具専門相談員研修)修了者でなければならない。
(ホウモンカイゴイン)
介護保険制度において、訪問介護や夜間対応型訪問介護などのサービスを提供する専門職。ホームヘルパーとも呼ばれる。介護福祉士の資格をもつ者や、都道府県知事または都道府県知事の指定する者の行う研修(介護職員初任者研修など)を受け、研修を修了した証明書の交付を受けた者が従事する。
(ホケンキュウフ)
保険事故(やはり社会保険の制度に共通する用語で、制度の対象となる出来事を指す。介護保険は「要介護状態」または「要支援状態」)が発生した場合に、被保険者に支給される、金銭や提供されるサービス・物品をいう。介護保険制度では、1割または2割・3割負担で提供されるサービスと、その利用料の9割または8割・7割を税金・保険料で補助することを指す。
(ホケンシャ)
一般的には、 保険契約により保険金を支払う義務を負い、 保険料を受ける権利を有する者をいう。全国健康保険協会管掌健康保険の保険者は全国健康保険協会、組合管掌健康保険は健康保険組合、国民健康保険は市区町村または国民健康保険組合、各種共済組合は共済組合。年金保険制度では、国民年金、厚生年金保険ともに政府である。高齢者医療確保法の保険者は医療保険各法の規定により医療の給付を行う全国健康保険協会. 健康保険組合、 市区町村、 国民健康保険組合または共済組合などである. 介護保険の保険者は市区町村であり、 実施する事務として、 被保険者の資格管理要介護認定・要支援認定、 保険給付、 地域主着型サーピス事業者に対する指定および指導監督地域支援事業、 市町村介護保険事業計画、 保険料等に関する事務が挙げられる。


(ミンセイイイン)
民生委員法に基づき、 各市区町村の区域に置かれる民間奉仕者、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱し、 任期は3年とされている。職務は、 ①住民の生活状態を適切に把握すること、 ②援助を必要とする者が地域で自立した日常生活を営むことができるよう相談・助言?その他の援助を行うこと、 ③援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するための、情報提供等の援助を行うこと、 ④社会福祉事業者等と密接に連携し、 その事業または活動を支援すること、 ⑤福祉事務所その他の閲係行政機関の業務に協力すること、 が規定されている。なお、 民生委員は児童福祉法による児童委員を兼務する。介護保険制度下では、 制度利用に関する相談や申請の代行. ケアマネジャ ー等と運携した利用後のフォローなどの役割を担っている。
(モニタリング)
ケアマネジャーが行うケアマネジメントの一過程.ケアプランに照らして状況把握を行い、 現在提供されているサービスで十分であるか、 あるいは不必要なサービスは提供されていないか等を観察・把護すること。モニタリングされた事項は、 ケアマネジャーのもとで評価され、 必要に応じてサービス担当者会議などによりケアプランの変更を検討する。


(ヨウカイゴシャ)
介護保険制度においては、 ①要介護状態にある65歳以上の者、 ②要介護状態にある40歳以上64歳以下の者であって、 要介護状態の原因である障害が末期のがんなど特定疾病による者をいう. 保険給付の要件となるため、 その状態が介護認定審査会 (二次判定)の審査・判定によって、 該当するかどうかが客観的に確証される必要がある。
(ヨウカイゴジョウタイ)
身体上または精神上の障害があるために、 入浴、排せつ 、 食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6か月間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状感で、 要介護状態区分(要介護l~5)のいずれかに該当する者をいう。
(ヨウカイゴニンテイ)
介護保険制度において、 介護給付を受けようとする被保険者が給付要件を満たしているかどうかを確認するために行われる認定. 保険者である市区町村が、 全国一律の客観的基準(要介護認定基準)に基づいて行う. 要介護認定の手順は、 被保険者からの申頂を受けた市町村が破保険者に対し認定調査を行うと同時に、 被保険者の主治医に意見書を求め、 これらの調査結果等を介護認定審査会に通知し、 要介護状態への該当、 要介護状態区分等について審査・判定を求める。
(ヨウシエンシャ)
介護保険法においては、 ①要支援状態にある65歳以上の者、 ②要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、 その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるものと規定されている。予防給付を受けようとする被保険者は、 要支援者に該当することおよびその該当する要支援状態区分(要支援l ? 2)について市区町村の認定 (要支援認定)を受けなければならない。
(ヨウシエンジョウタイ)
身体上もしくは精神上の障害があるために、 入浴、排せつ、 食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6か月間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、 または身体上もしくは精神上の障害があるため、 6か月間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態で、 要支援状態区分(要支援l ? 2)のいずれかに該当する者をいう。
(ヨウシエンニンテイ)
介護保険制度において、 予防給付を受けようとする被保険者が給付要件を満たしているかどうかを確認するために行われる認定。保険者である市区町村が全国一律の客観的基準(要支援認定基準)に基づいて行う。要支援認定の手順は基本的には要介護認定と同様(要介護認定と同時に行われる)。
(ヨボウキュウフ)
介護保険における要支援認定を受けた被保険者に対する保険給付であり、 要介護状態にならないよう予防することを目的とする。


(リハビリテーション)
心身に障害のある者の全人間的復権を理念として、 高齢者や障害者の能力を最大限に発揮させ、 その自立を促すために行われる専門的技術をいう。
(リヨウシャフタン)
福祉サービスなどを利用した際に、 サービスに要した費用のうち、 利用者が支払う自己負担分。介護保険法においては応益負担(定率負担)が原則とされ、 その負担割合はサーピスに要した費用(利用料)の1割または2割である。なお、 施設入所などにおける食費や居住閂(滞在費)については、 全額利用者負担となっている(低所得者に対する軽減策[特定入所者介謹サ ーピス費の支給]はある)。
(レクリエーション)
レクリエーションはラテン語が語源とされ、英語では元気回復や滋養等が古い用例としてあり、日本の初期の訳語では、復造力や厚生などがある。現在では、生活の中にゆとりと楽しみを創造していく、多様な活動の総称となっている。介護福祉領域などでは、人間性の回復などの理解もみられる。介護保険制度下では、通所介護や施設などで行われている。